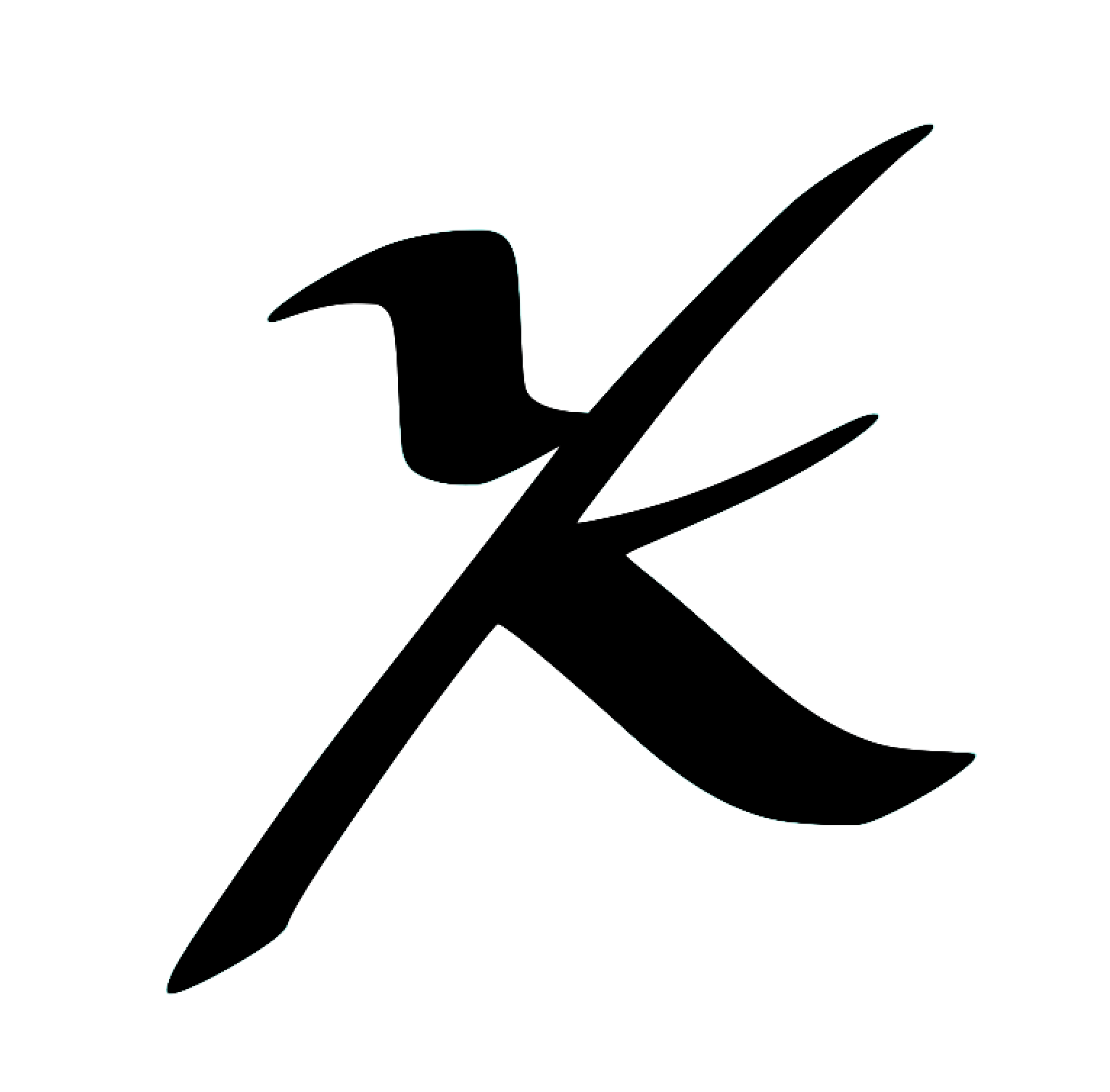まず、素晴らしい作品でした。
スクールカーストをベースにそれぞれの鬱憤、葛藤が効果的に描かれます。そして小さな昇華を重ねては、また葛藤。
結局のところカーストや鬱憤、閉塞感を解消できるのは自分でしかない。
「そんなチャーリーに乾杯。」「僕は無限だ。」正にそんな映画です。
作品情報
制作年 2012年
制作国 アメリカ
上映時間 102分
ジャンル ドラマ
監督
スティーヴン・チョボスキー
キャスト
ローガン・ラーマン(チャーリー)
エマ・ワトソン(サム)
エズラ・ミラー(パトリック)
メイ・ホイットマン(メアリー・エリザベス)
ジョニー・シモンズ(ブラッド)
あらすじ
小説家を志望する16歳の少年チャーリーは、高校入学初日にスクールカースト最下層に位置付けられ、ひっそりと日常を送っていた。
まさに「ウォールフラワー(壁の花)」である。
ところが、陽気なパトリックとその妹である美しく自由奔放なサムとの出逢いにより、彼の日常に明るい光が射し始める。
しかし、チャーリーの昔の事件をきっかけに物語は、思いも寄らない方向へ…。
感想・考察
チャーリーの手紙は、誰に宛てたものだったのか。
度々今作の中に、挿入されているチャーリーが手紙を書くシーン。”友達”へ宛てた手紙であるということは間違いありませんが、気になるのはそれが誰だったのかということ。
今は亡き叔母さん?自殺した親友?サム?パトリック?幻覚?色々と頭を巡らせましたが、これを裏付ける根拠が、どれもこれも薄い…。
そこで腑に落ちた答えは、自分自身へ宛てた自伝的な小説であるということ。チャーリーは作家志望でありまして、さらに叔母さんにもサムにも小説を書くことを勧められていました。また、彼は叔母さんのこともサムのことも好きであると明言しています。精神的問題を抱えていたチャーリーですので一般論が通じるのかわかりませんが、一般的に好きな人から言われた言葉であれば前向きに捉えるのが人間というものであると思われます。すると、好きな人から勧められたのがモノ書きであれば、実践するはずです。
そして、それをこちら側に語りかけるかのように進む物語。彼の過去を回想伝えることで、追体験しているかのようにも感じるのです。
どこまでが、映画なのかの真実で虚構か腑に落ちない。この手法によって観客を引き込むんですね。スティーヴン・チョボスキー監督の作品はというと、前回レビューした映画「ワンダー」も素晴らしい作品でしたが、今作はまた作風が違って好奇心がふつふつ湧き上がるするような演出が面白い。それが顕著に表れているのこそが、まさに手紙の回想シーンでした。
また、これはメタ構造というようです。
スクールカーストから見えたもの
今作は全体を通して学校がメインの舞台として描かれていますが、その中でも印象的なのがスクールカースト。これは学校空間における生徒同士に自然発生する優越関係・上下関係などの序列関係を表現したものです。日本でもスクールカーストなるものを感じる機会というのは往往にして存在するわけですが、
例えば日本では、カースト上位はパリピ、美男美女、スポーツマン、金持ちなどが占めるでしょう。そして所謂普通の子供がいて、最下層がオタクや隠キャと呼ばれる子供となるわけです。まず序列関係があるということ自体が平和ではないですね。しかし、思うのはそれを構成している要素として確かに自分も存在するわけです。
一方アメリカのスクールカーストは、さらに階級が細分化されスクールカーストの色が強いようです。今作では、「ゲイとゴスのキスシーンだ!」というセリフがありますが、これは明らかに本来は自虐として用いられる言葉ですが、彼らは仲間内にそれを見せることで、自分たちを肯定していたのかもしれません。これはスクールカーストのような階級制度への反骨心であり、悲痛な叫びであったのでしょう。すると、これは明らかに社会へのメッセージの強い投影したシーンであって、社会派ドラマとしての監督の叫びが間接的に表現された映画に見えてくるのです。
講義によって学年問わず生徒が混在しているのも印象的です。そのせいで、チャーリーは高校が終了するまでの日数を数え、学校が終了するのを心待ちにし、日々に閉塞感を覚えるばかりでした。またチャーリーの孤独を効果的に表現するカメラワークも絶妙です。
一方で混在しているお陰でチャーリーはパトリックとサムに出会えたのも事実です。日本もこのような教育スタイルの方が良いのではないのかと思わざるを得ません。年齢という普遍的なもので縛りをつけて教育すること自体が個性や好奇心を潰しかねないということも思わせてくれるからです。個性や多様性を唱えるのであれば、その縛りは極端なものですから。
鬱憤の昇華と音楽と
また音楽と映像の調和が美しい映画でもあります。ミュージカル映画は人気の映画ジャンルの1つですが、個人的には好みません。音楽と映像が喧嘩してしまっているように感じるからです。その点、今作の音楽シーンはどれもこれも意味合いが良い意味でストレートに感じられ心地よいです。
また、爆音で音楽を流すパトリックにサムが注意すると「耳が潰れることこそがロックだ」をいうセリフが、ゲイやゴスというマイノリティでいることを肯定するマインドそのものなのだとも思い知らされます。他には「Cマイナス 平均以下だー!」と叫ぶのパトリックも日常や学校という鬱憤からの昇華を助けます。それがチャーリーの自己肯定の意思を刺激し成長へ繋がったのも間違いなのでしょう。
そして今作の斬新で個人的に好む演出が正にそれです。基本的に映画は、序盤・中盤の鬱憤を終盤で昇華します。これの最たるものがサスペンス映画です。この良さは時系列に沿って2時間前後に集約されたものがラストで一気に解放されることです。一方で今作の昇華の仕方は映画全体としての昇華はもちろんあるものの、小刻みに鬱憤から昇華を繰り返していきます。つまり、時系列だけが鬱憤の解消ではなく、同時進行で様々な感情が渦巻いていていることを表現しているように感じるのです。これはチャーリーをはじめとするマイノリティが感じる閉塞感の複雑さを的確に表現しています。この表現が素晴らしい。「時間が解決する」ではないことを物語るようでもあるので若干悲しい気もしますがリアリズムではあります。
「僕は無限だ」
先述した時系列が鬱憤の昇華ではないといったものの、クライマックスのチャーリーの演出、伏線回収は見事であります。序盤から閉塞感を溜めてはパトリックやサムの友情、時には恋が解消するわけですが、結局のところマイノリティーにとって外的要因だけでは葛藤を昇華しきれないのです。
しかし、意図的に自分を認めたチャーリーは「僕は無限だ」と言い放ち、成長を観客に見せてくれたのです。めでたしめでたしな作品でした。