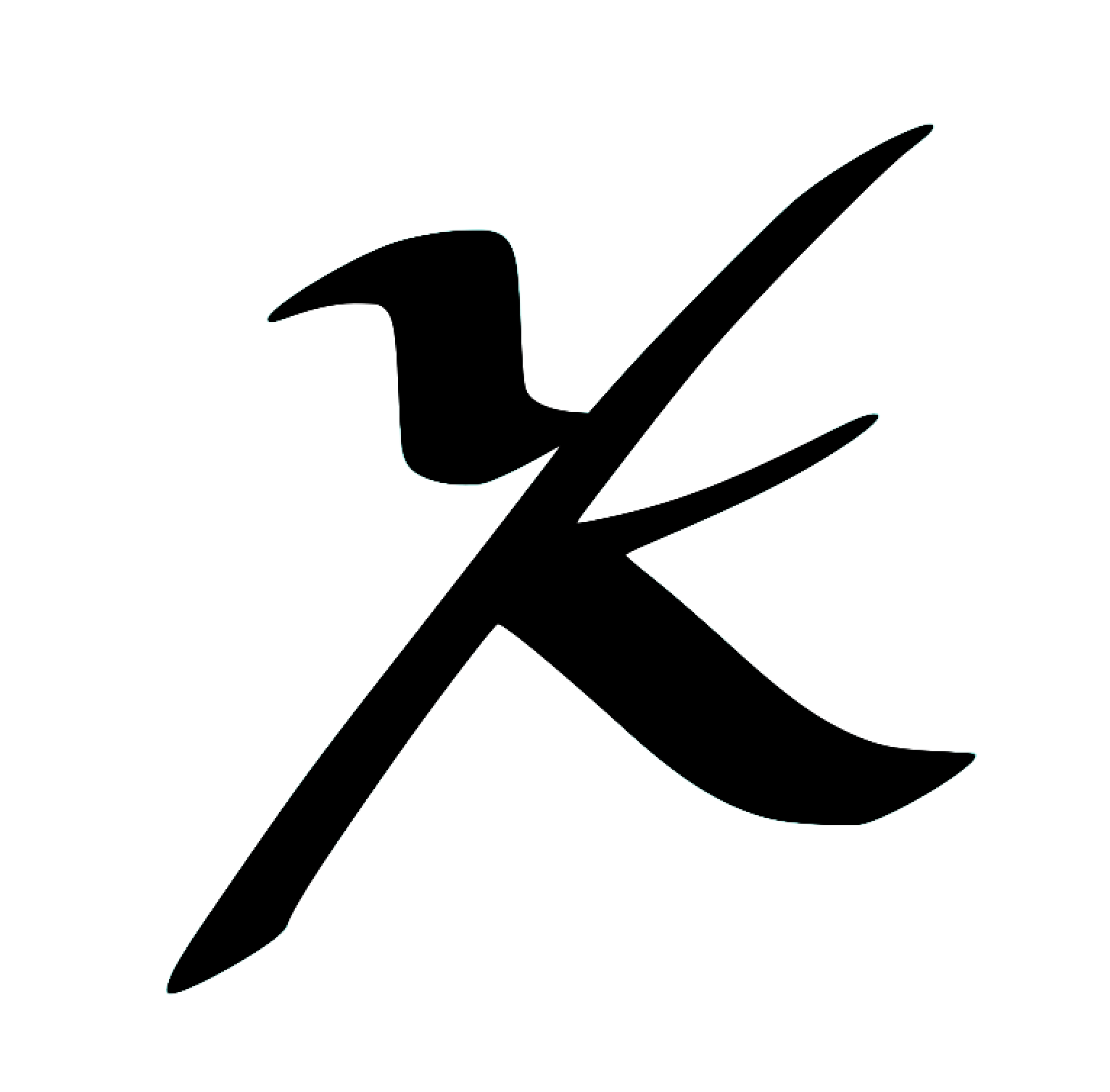主体であるバーディ自体の進展のなさ。
アルのバーディに対する一種の憤り。現実との対比として描かれる戦争のネガティブ。
解放するための手段がなぜ野球ボールなのか?もっと効果的な対象があるのではないのか。
など、この物語には様々な鬱憤が散りじりになっています。
ラストで昇華される鬱憤。それはもちろんフォーカスすべき点でしょう。
しかし、その鬱憤を蓄積させる技法。それこそが、この映画の面白さでした。
作品情報
製作年 1984年
製作国 アメリカ
上映時間 120分
ジャンル ドラマ
監督
アラン・パーカー
キャスト
マシュー・モディーン(バーディ)
ニコラス・ケイジ(アル)
ジョン・ハーキンス
サンディ・バロン
カレン・ヤング
あらすじ
ベトナム戦争のショックにより精神病院へ入ったバーディは心を閉ざし、鳥になることを幻想している。
同じくベトナム帰還兵であり高校時代の親友アルはバーディの心に寄り添う。
アルに残された時間は一刻と少なくなるもののバーディは依然として心を開かない。
感想・考察
社会的なメディアとして 米国におけるベトナム戦争のターニング
昨日の「7月4日に生まれて」と同様にベトナム戦争が絡むの作品でした。
戦争の絡む映画やその類のアクションなどはあまり見てきませんでしたが、ベトナム戦争に関する映画はたくさん撮られているのですね。
それだけ、ベトナム戦争というのは映画大国であるアメリカにおいて映画的・歴史的な、ターニングとなった出来事だったのでしょう。
映画が社会を映す反射的媒体であるとすれば、その鏡としての映画的メディアの数量で、その当時の社会性が見えてきます。
まさに、ベトナム戦争はそのような社会的ポイントであるのでしょう。
空と檻と。戦争への暗示
大いなる空と閉鎖的なバーディの閉じ込められている檻との対比から始まる物語。
鳥が枝に佇むかのようなバーディの座り方。
この表現は戦争がもたらすものネガティブにの暗示と捉えることができます。
言い換えれば、オープニングから一種の恐怖体験が始まったのです。
さらには、血をはじめとするグロテスクを交えながらの戦争の回想に加えて、戦争の行く末を比喩的対象としてのぐるぐる巻きの包帯。
具体的であり直接的、抽象的であり間接的、問わず戦争というネガティブな歴史に対する暗示は、何処とない。
その何処となさが、当然の歴史であり隠しようのない真実であることを物語っています。
それが怖い。
表現技法の隆盛とトラディショナルな技法
バーディが屋根から飛び降り怪我をするシーンです。
現代のスタントやCGなどの技法が現代的でありリアルとも厭わないレベルのものであるとすると、1980年代ということもありスタントの不十分さを感じるシーンもあります。
つまりは現代的技法が使えるのであるのならば、そのようなシーンは生まれうることもなかったのかもしれません。
しかし、その未熟とも取れるシーンがスローモーションや反復で映画として心地よく解消されているのです。
過去とリアルの対比に関しても観客を離さない程の良い、切り替わり具合です。
「飛ばねぇ豚はただの豚だ」に見るエロス
ジブリの「紅の豚」で有名マルコの「飛ばねぇ豚はただの豚だ」という台詞ですが、バーディの鳥への憧れ、鳥でないのであれば意気消沈の姿と異様に重なります。
鳥的であればそれは生を感じるエロスであり、檻にいるのであれば死を意味するタナトスを感じます。
もし何かしらのインスパイアを受けているとするのであれば、後発の「紅の豚」の方ですが。
コミュニティの有用性 犯罪心理的に
一般論で言えば、笑みを浮かべ屋根から落ちる。全裸で鳥と寝る。というのは明らかにサイコパス気質です。
つまり、少年時代のバーディの病的なまでに鳥への執着心があるわけです。
そして鳥であるということは飛行することと同意であるので、飛べない鳥は鳥ではない。
鳥でないのであれば価値がないとも取れます。
すると、鳥への執着や憧れのあったバーディは檻の中に閉じ込められることによって生気の消失に繋がりにつながったのではないのかと考えられます。
自由の象徴としての鳥の飛行があるのであれば、檻という閉鎖された屋内には、バーディの鳥的な自由は存在しないのでしょう。
檻の中の鳥は飛び方を忘れるかの如く、バーディは衣食住といった人間的な本質を失ったのではないでしょうか。
つまり、バーディの思う鳥的自由がないのであれば、鳥に投影していた自分自身の価値もなくなってしまうということです。
これは一つの物事にしか自分の心身を許せなくなった人間の末路であるとも感じ取れます。
例えば、犯罪心理的に家族や友人、職場、など自分の拠り所であった唯一のコミュニティを失った人間は、自傷行為や他人への誹謗中傷、暴力で自分を保とうとする場合があります。
また、エネルギーがなくなり鬱状態になるという場合もあります。
後者はバーディのそのような鬱的な心理に非常に重なるのです。
バーディにとって自分を形成していたコミュニティは鳥であったので、それに関われないという状態だからです。
自虐としての鳥的主観のカメラワーク
鳥的なカメラワークは面白い技法ではあります。
しかし、鳥ではないという本質的には叶わないというバーディを自虐しているようなシーンでもありました。
現に空を飛びたくても落下するだけのバーディの姿が映し出されていましたから。
鬱憤の蓄積に基づくカタルシスの高揚
齢とともに鳥への憧れが強くなっていったバーディですが、なおさら解放するための鍵となるのはボールなのか?という疑問を抱きました。
なぜボールである必要があるのか。鳥が最も効果的なはずです。
しかし、その疑問はあえて視聴者に見せた・抱かせた意図的な鬱憤であるように思えます。
ラストのコミカルなシーンを見れば、その効果は薄れてしまいますが、元を辿ればそのような本質と外れているが故に抱かせる疑問が大きく鬱憤の構築を下支えしているのではないでしょうか。
ボールという存在が、敢えて中途半端な鬱憤解消としてのツールで作あるとすれば、この脚本は本当に凄いものです。
ラストを高揚させるための凝りに凝った技法です。
それぞれの自由にために
生まれ持った自分の顔という生きていく術や親友であるバーディを失ったアル。
鳥的自我を失ったバーディ。
2人が話せた時のカタルシスなぜか薄かったのは残念でした。
そしたら、それさえもラストでコミカルに全てを昇華させてくれます。バーディは自由を、アルは親友を再び手に入れて。
https://amzn.to/3zQHpMv