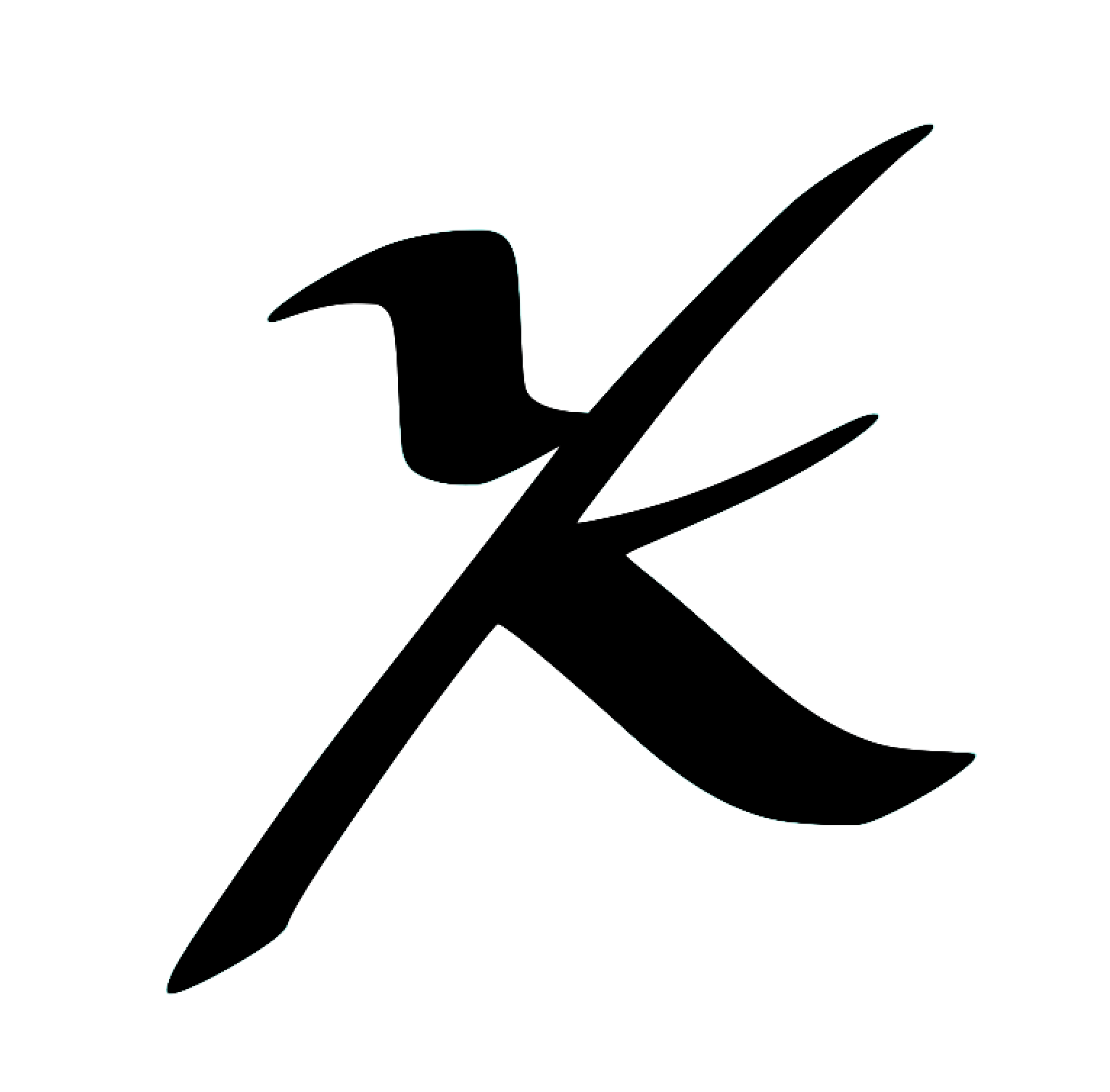全世界で800万部以上を売り上げたR・J・パラシオのベストセラー小説「ワンダー」をベースに映画化。
J・D・サリンジャーの再来と呼び声の高い監督であり脚本家スティーブン・チョボウスキー。
彼の社会派な作風の中にも暖かさを垣間見ることのできる今作。
個の立つキャストの点と点を紡いで線に、そして映画を通して面に。
作品情報
制作年 2017年
制作国 アメリカ
上映時間 113分
ジャンル ドラマ
監督
スティーヴン・チョボスキー
キャスト
ジェイコブ・トレンブレイ(オギー)
ジュリア・ロバーツ(イザベル)
オーウェン・ウィルソン(ネート)
マンディ・パティンキン(トゥシュマン先生)
ダビード・ディグス(ブラウン先生)
あらすじ
10歳の少年オーギーは生まれつき人とは異なる顔を持っていた。
そんなこともあり、幼少期から彼は母イザベルと自宅で学習を行なってきたが、小学5年生を機に学校へ通うことに。
同級生と仲良くなりたいと願う彼だったが生まれつきの顔によって、それは容易には叶わない。
避けられたり、偏見の目で見られる彼だったが、徐々に変化が…。
感想・考察
個の立つキャスト 点が線に、映画を通して面に
凶悪監禁事件を基に描かれ、2015年に映画化された名作「ルーム」で天才小役と称されている、今作の主人公ジェイコブ・トレンブレイ。数々の映画に出演し、名女優としての位置を確立した、今作の母親ジュリア・ロバーツ。そして父親オーウェン・ウィルソン。
そんな現代アメリカ映画界のスター達。それぞれを調和させ、スパークさせたのがスティーブン・チョボウスキー監督。これらの俳優陣は、映画の中でポジティブな意味で非常に個が立つ。ジェイコブ・トレンブレイは先ほどの「ルーム」。ジュリア・ロバーツであれば、注目を集めるきっかけとなった「マグノリアの花たち」、ゴールデングローブ賞を受賞した「プリティ・ウーマン」、ベストセラー小説を基にした「食べて、祈って、恋をして」。オーウェン・ウィルソンであれば愛犬との絆を描いた「マーリー」、「ミッドナイト・イン・パリ」。どの作品においても、それぞれの視点がベースにあり、彼らの時間で物語が構成されている。しかし、今作では、それらが互いに圧迫せず、心地よくラストの昇華に向かっている。
これは監督の才に他ならないのではないかと感じられる。彼はもともと小説家であり、彼が脚本と監督を務めた「ウォールフラワー」は、批評家たちからJ・D・サリンジャーの「ライ麦畑でつかまえて」の再来と絶賛されている。さらに、彼が脚本を手がけ、今作の前に公開された「美女と野獣」は日本で大ヒットを記録している。
彼の作風は、少年の視点をベースに描かれ、学校で起こる普遍的な出来事を暖かく見守る親のような優しさを感じる。また、厳しくも優しいアメとムチが物語の中にあり、それ故に最後は心地よい昇華(成長)がある。この作風には彼の幼少期が起因しており、彼の過去を投影した等身大の物語が、観客の心に響くのではないかと感じる。だから、今作においては際立つキャストの個性を暖かく包括して点から線に、スパークを起こしラストで昇華し、線が映画という面になったように感じる。
オギーにとっての失礼とは
自分の顔に嫌悪感を抱き、外出中ヘルメットを被るオギー。今作の印象的なシーンに、好奇心からオギーの顔について質問してしまう子供達を映したシーンがある。質問にオギーが戸惑うと、他の子供は「失礼だからやめてあげて」と、その子を抑制する。
好奇心でオギーの顔が気になる子供の好奇心は仕方がない。むしろ、それを抑制する方が本質的にはオギーにとっても失礼に値する。
日本では、この類の社会規範やモラルという名目で、好奇心を抑制する場面は他国にも増して強い。すると、極めて日本的な映画にも見えるし、オギーへの質問をやめてしまうことで、彼の求める本質的な友人関係には発展することはないということを示唆させる。
それを昇華するかのような、母親イザベルの「心の狭い行いは大きな心で許してあげて」「ヒトの顔には印がある」という言葉がシナジーする。
多角的なストーリー展開
今作の見所はオギーの心の再生だけではない。もちろんオギーがベースにはなるが、それによって弊害を受けた人々のバックグラウンドを描く多角的な物語が、様々なことを物語る。
唯一の友人であったジャック。オギーによって両親との関係性を希薄に感じてしまうオギーの姉のヴィア。彼女の親友であるミランダ。それぞれの視点からオムニバス的に展開されるストーリーが多角的で奥深さを演出している。
紛れもなくオギーの葛藤を描かれているし、それによって人の本質を垣間見ることができる。それは良い面も悪い面も。そして挿入される、愛犬デイジーの偏見の目を持たない姿が暖かくも「デイジーは僕が退院するといつも待っててくれた」というオギーのセリフが切ない。そして、デイジーにも寿命があり、その別れを示唆させるシーンを挿入することで、オギーの葛藤や嫌悪感はさらに深刻なものになるし、孤独感を表現している。
オギーをいじめた男友達との若いのシーンがないことが少々残念に見えたが残念ではなかった。
彼は間接的であったが、謝罪していたし、心で通いあっていたという事を示唆させていたのかもしれない。すると、その曖昧な演出がまた良いのかもしれない。
補完的だが絶対的な母親の存在
オギーがメインにはなっているが、姉ヴィアに映る視点がまたオギーの立ち位置をシナジーしている。「ママは本質を見抜くいい目を持っている」というのは非常に正に本質的なワードである。映画「ものすごくうるさくて、ありえないほど近い」にも母の持つ偉大さが語られている。それと同様に母親という存在は普遍的だが、普遍的であるが故に見失いがちな母親の存在感を感じることができる。
過保護になりがちなのが現代の母親像だろう。しかし、本来他の子供達にも増してオギーの心配をしたいはずにも関わらず、「大事なのは自分がワクワクするようなテーマを選ぶことよ」この言葉が出てくることが偉大すぎる。それが子供を信じることであり、愛だと思うから。そんな母親イザベルが、夫ネートからメガネを取るシーンがまた良い。
ヘルメットが不要になったオギー
後半に進むにつれて、オギーはヘルメットが必要なくなり文字通り素顔で生活するわけだが、可視化された演出もさることながら、「誰だって一生に一度くらい拍手を浴びるべきだ、友達だって、先生だって、僕だって」オギーのこの言葉が物語ることこそ、今作の完璧なる昇華だろう。この思考に至ったのも誰でもない、自分のおかげである。でもその自分を構成しているのは、家族や友人、恩師の存在は絶対的である。それに感謝の念を込めたオギーに拍手を送りたい。