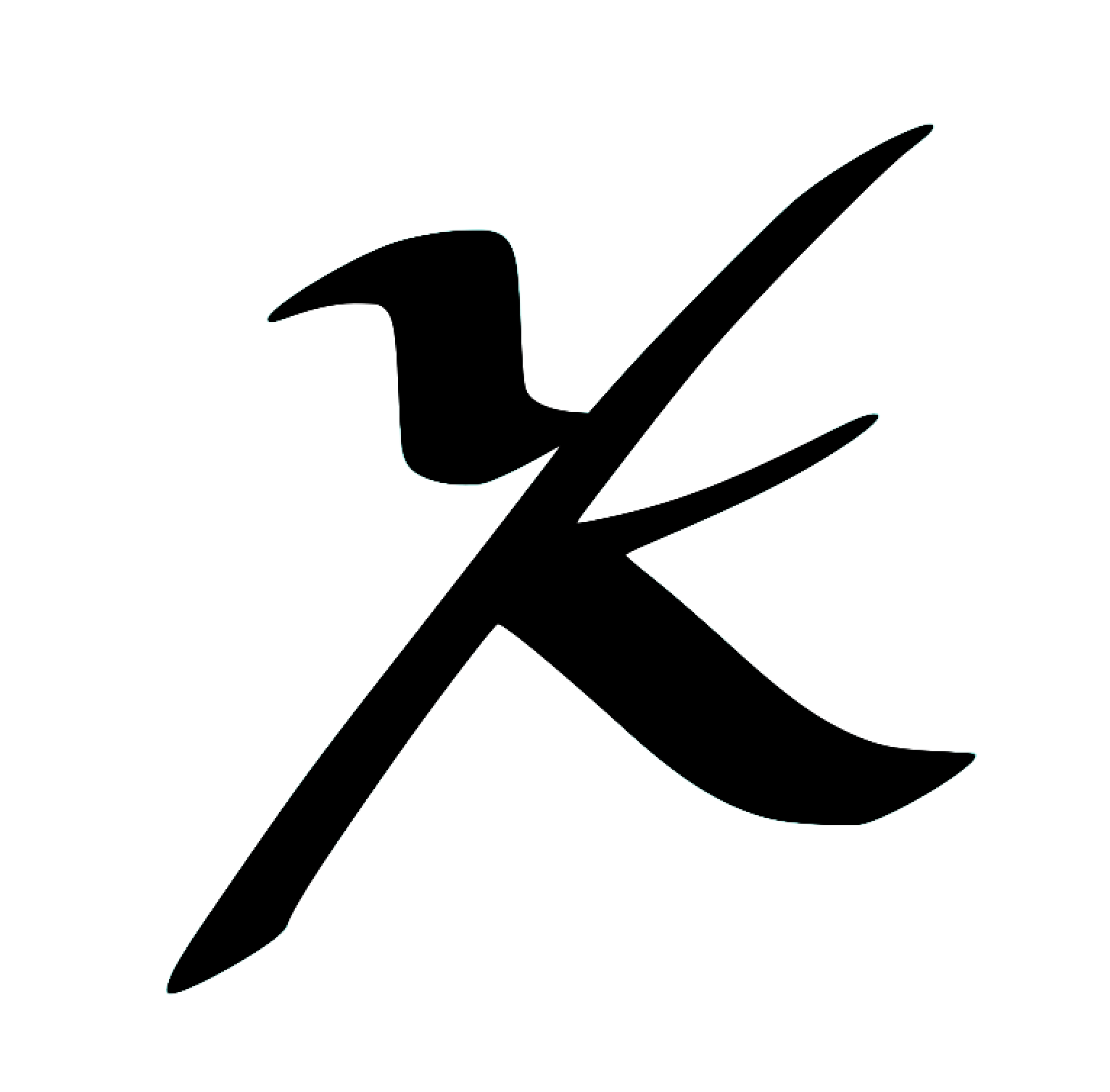ムーブメント、台湾ニューシネマの代表としての今作。
とにかく長い、しかし長いのは理由がありました。
クリエイターの鬱憤、葛藤、昇華。
確かに具現化されていたように感じました。
コントラストが美しい作品でしたが、現実はコントラストされていない、つまりは現実に忠実で苦しい。
作品情報
制作年 1991年
制作国 台湾
上映時間 236分
ジャンル ドラマ
監督
エドワード・ヤン
キャスト
チャン・チェン(シャオスー)
リサ・ヤン(シャオミン)
ワン・チーザン(ワンマオ/リトル・プレスリー)
クー・ユールン(フェイジー)
タン・チーガン(シャオマー)
あらすじ
1961年の台湾・台北。夜間中学に通いプレスリーに憧れる14歳の少年スーは不良グループ・小公園に属するモーやズルと毎日悪さを。
ある日スーは少女ミンと知り合う。彼女は小公園のボスであるハニーの女で、ハニーは対立するグループ・軍人村のボスとミンを奪い合い、相手を殺し姿を消していた。
それは台湾初の未成年による殺人事件だった。
ミンへの淡い恋心を抱くスーだったが、ハニーが突然戻ってきたことからグループの対立は激しさを増し、スーたちを巻き込んでいく。
感想・考察
「台湾ニューシネマ」の代表格
80年代から90年代にかけて台湾映画界に旋風を巻き起こした台湾ニューシネマ。
これは、従来的な商業性の強い映画作りとな異なり、台湾出身の若手クリエイターによる、台湾社会の根幹にフォーカスしたニューウェーブである。
映画界におけるムーブメントの代表格といえば真っ先に上がるのが、フランスのヌーヴェルヴァーグ。
コアな映画ファン、映画に関心の強い方であれば、誰しもが一度は通る映画群ではないだろうか。
ヌーヴェルヴァーグの代表格「気狂いピエロ」はこちら。
台湾ニューシネマ、その表面を擬えればムーブメントとしては如何にもそれらしく、聞こえはいい。
しかし、その背景には低迷した台湾映画界はもとより、クリエイターとしての痛烈な苦悩や葛藤が遺憾無く表現されているようにも感じる。
すると、本質的にアーティファクトとしての映画であるということも感じさせられる。
故に、現代主義的な思想の投影された苦しい作品であるようにも感じるのである。
台湾ニューシネマにおける名高い映画監督といえば、日本でも認知度の高い今作のエドワード・ヤン、並びにホウ・シャオシェンである。
彼らの一見、実験的で挑発的な作風は多くの人間の心を虜にする一代ムーブメントとして確立され、現代映画界に語り継がれている。
その代表格に相応しいのが今作である。
映画界の巨匠マーティン・スコセッシも今作を愛するというのも理解に容易である。
このニューウェーブの特徴といえば、やはり社会を投影する鏡として忠実性。
また、映画的メディアとしての写実性である。
本来、映画が娯楽であるという大前提があるとすれば、この忠実性や写実性は映画の方法論としては時代を逆流する表現技法である。
しかし、その時代という虚構によって抑圧されたエネルギッシュな若手クリエイターの創造における反骨心を増大させたのは、理解容易性が極めて高い。
そう思えば、今作は実話をベースにして描かれているということもあり当然ながら台湾ニューシネマ的な作品である。
4時間あまりの超大作として
今作は上映時間236分と、映画の中でも極めて時間を有する超大作である。
しかしながら、その長さを感じさせないのは、写実性が顕著で映画でありながら身近な社会でありながら学校という誰もが経験する世界を投影した身の上話かのように見えたからである。
これは、完全な主観的な価値観だが、友人との身の上話は何時間でもしていられる。
娯楽でありながら実に等身大で、映画をみるというよりも、映画というフィルターを通してキャストの視点で物語を追体験することができる。
もちろんこれは他の方には当てはまらないだろう。
単純に長い作品として退屈に感じるかもしれない。
話は変わるが、2020年を目処に通信規格が4GからWiFiと肩を並べる通信速度が期待できる5Gが実装される見込みだ。
それによると今作のような大作においても5秒程度でダウンロードが完了してしまう。それによって、さらなる動画の隆盛はもちろんのこと、映画のモバイル化も進む。
すると今作のような超大作であっても、より身近になる訳である。
また、既存のスキームを覆すという意味では、テクノロジーの隆盛は利便性の向上でありながら、全く破壊的である。
ニューウェーブとしての今作も極めて破壊的な作品であるが、どこか優しい。
優しいというのも表面的な優しさではなく、愛でるといったところか。
エドワード・ヤンの映画を愛でるが故の、現実への鬱憤、そして今作に対する鬱憤の解放としてのアウトプット。
物語こそネガティブ要因だらけであるが、根幹には映画を愛でる彼の思いが如実に表現されている。
だから4時間を超えても、社会を投影し、”社会を残す”手段として映画として具現化したのだろう。
演出のコントラスト しかし、物語は悲しいほどに現実と忠実
今作の演出は光と影の使いが非常に巧い。
というのも、陰陽のコントラストが悲しいほど綺麗に見えるからである。
メインで描かれている子供たちの心情的は、一見すると明らかに陰、不良であり人を傷つける姿からそれは明らかである。
しかし、願望的でもあるが本質は陽であるはず、あるべきである。
社会に飲み込まれてゆく、思春期、中学時代。
その過渡期にグレーを通り越し、黒、つまりは陰になる。
それが、実は青春時代を物語るものであり、一種の正規ルートでもある。だから思春期と反抗期は相反するものでもない。
本意はわからないが、今作のジャケットがグレーなのも、もしかしたらそこに起因しているのかもしれない。
すると、制作側は伝えたかったのは、黒にも白にもなれない、いわば不良にもなれない子供達の惨めな反抗なのかも知れない。
それが、明らかに思春期でもあるし、反抗期でもある。
だからその若さ、純粋無垢とも思える少年たちの姿が美しく、そして映画というフィルターを通した時に”巧い”のである。
そんなコントラストの巧さを語る割に、今作における現実は悲しいほど忠実である。
つまり、物語はコントラストされず極めて現実に忠実なのである。
それがとてつもなく悲しくも思える。
なぜなら、結局は人を傷つけるという結果に終点があったのから。
そして、煙に巻かれたような、霞みがかったような世界観が見事に余韻を残す。
半分揶揄的な意味を込めると、官僚的な教育の”犠牲”になった子供達。
彼らは社会に諦めが肝心だと言い、かたや努力で未来をつかめと言われる。
この矛盾が重くのしかかって来た。
そして語る、「大人はめんどうだよ、大人になったらわかる」と。
正に当時の台湾社会を浮き彫りにしたワードである。
社会に対する葛藤の行き場が作品作りであり、台湾ニューシネマであるならば、このワードだけでも挑戦的な作品であると言える訳である。