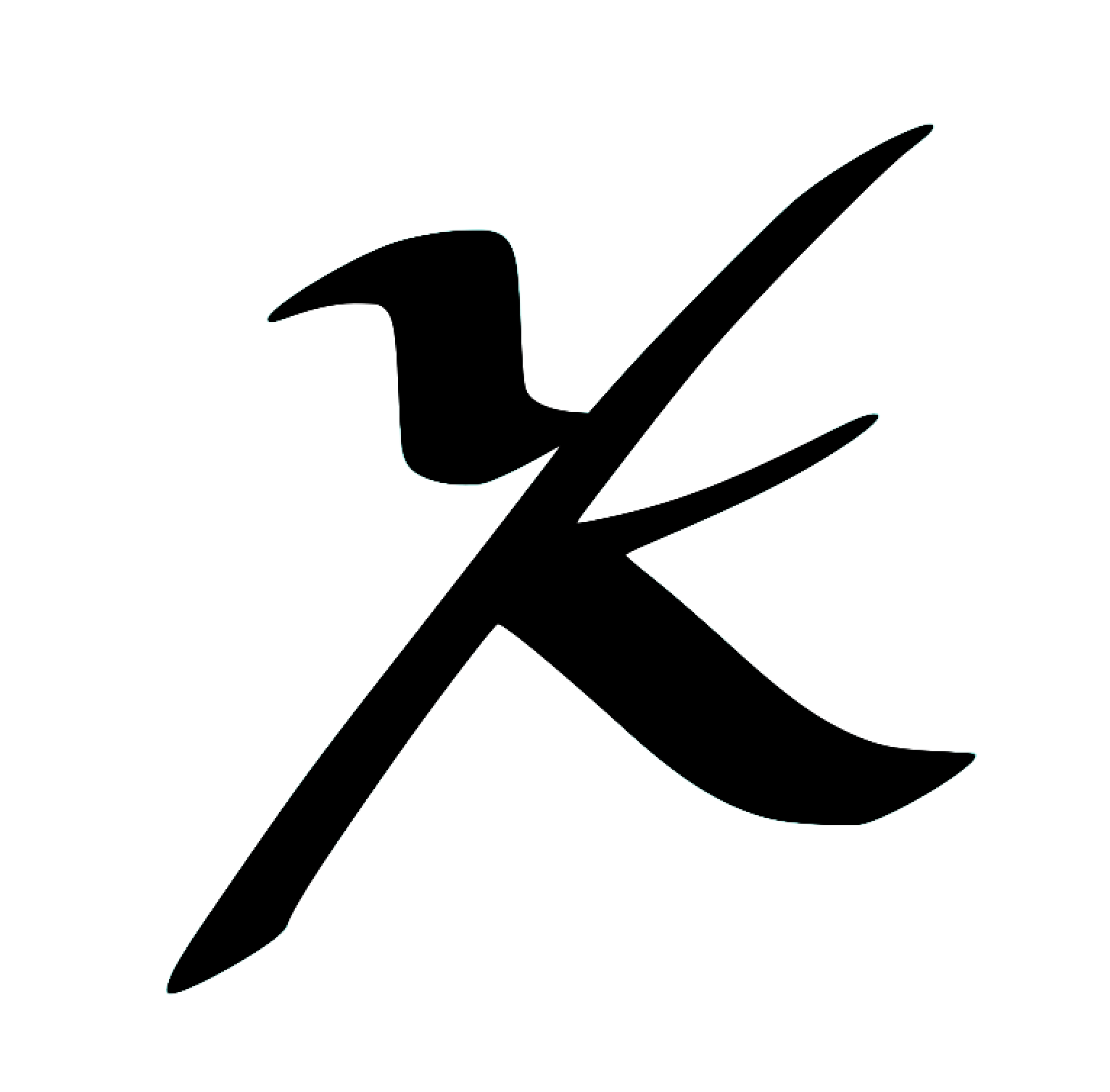「ライ麦畑でつかまえて」は知っているけれど、原作者については知らないことも多い。
今作は自叙伝的な作りになっていて、J・D・サリンジャーのバックグラウンドから、ベストセラーを生み出し、その後の末路までを描いている。
反ユダヤや物書きとして抱える憤りや葛藤など心理的描写などドラマチックな物語に、ニコラス・ホルトとケヴィン・スペイシーはベストマッチ。
作品情報
製作年 2017年
製作国 アメリカ
上映時間 109分
ジャンル ドラマ
監督
ダニー・ストロング
キャスト
ニコラス・ホルト(J・D・サリンジャー)
ケヴィン・スペイシー(ウィット・バーネット)
ゾーイ・ドゥイッチ(ウーナ・オニール)
サラ・ポールソン(ドロシー・オールディング)
ルーシー・ボーイントン(クレア)
あらすじ
1939年、作家を志しコロンビア大学の創作学科に編入した20歳のサリンジャーは、大学教授ウィット・バーネットのアドバイスで短編小説を書き始める。
出版社への売り込みを断られ続ける中、ようやく掲載が決定するが太平洋戦争が勃発。
それによって、その掲載は見送られてしまう。
召集により戦地に赴いたサリンジャーは戦争の最前線で地獄を経験し、終戦後もそのトラウマに悩まされながら、初長編「ライ麦畑でつかまえて」を完成させる。
この作品の成功により、突如として名声を手に入れたサリンジャーだったが…。
感想・考察
「ライ麦畑でつかまえて」は知っているけれども。
「ライ麦畑でつかまえて」は知っているけれども、J・D・サリンジャーについては知らないという人が多いと思う。大体の物語がそうであるように、原作者については明確ではなかったりするもの。かくいう自分は正直なところ原作も原作者も名前しか知らないという始末。そもそも僕は本を読むという習慣が全くなくて、本を読み始めたのも3年前くらいの大学2・3年生くらいから。といっても、小説は全くといっていいほど読んでいない。映画を日常的に見るようになってから、ようやく原作とか小説とか、物語に関心を持ちようになって、今は仕事で物語のシナリオなんかも書くようになっている。そう思えば僕にとって映画の与えてくれた影響はとても大きいのだと改めて思わせるし、やろうと思えば仕事でもなんでも大抵のことはどうにかなると勝手に思っている。これからYouTubeでもやろうかとも思っている。
話を戻すと、「ライ麦畑でつかまえて」は当時の人々に多大な影響を与えた必読書として知られているらしい。僕の好きな「ドラゴンタトゥーの女」の原作である「ミレニアム」シリーズも必読書らしく、今尚発行部数は伸びているらしい。またそれそうなので今度こそ戻すと、今年2019年でJ・D・サリンジャーは生誕100周年ということになるらしい。そう思うと今こそ観るべき作品だとも思えてくる。彼の人生の中でも特筆すべきは、今作の原作となった作品がベストセラーになった後にも表舞台から姿を消し隠遁生活を送っていた。ということ。今作はまさに彼の成りあがりと隠遁生活までを描いた作品。なぜ”成りあがり”なんて揶揄するような言い方をするかといえば、それも理由がある。僕自身が彼を揶揄するという訳ではなくて、当時の社会と彼のバックグラウンドが関係しているので”成りあがり”と言わせてもらう。
名作と呼ばれる作品は数え切れないほどあるけれど、大体は原作者について知らない。それが通例というのも少し呆気なく、悲しいような気もする。だけれど、今作はそうでもなくて現代にも語り継がれているし、何より映画化されるということで名作たる所以を知らしめている。さらに、J・D・サリンジャーは表舞台から姿を消したことで、一層どこか神格化された人物・作品になっているようにさえ感じる。そんな彼の代名詞的作品が「ライ麦畑でつかまえて」ということだ。他にも、亡くなった・表舞台から姿を消した、ことによって神格化されたり、伝説的な存在になる人物というのは確かにいて、いなくなることで実績が際立ったりする効果は確かにあるのだろう。サリンジャーはそういう意味で姿を消した訳ではないけれど。
J・D・サリンジャーの自伝的作品
今作は、そんな知られざるサリンジャーの自伝的作品として映画化されている。彼はもともと裕福なユダヤ信者の家庭に生まれたが、当時は反ユダヤの動きが強く苦労もあったそうな。これが先ほどの”成りあがり”の所以である。裕福にも関わらず、社会的には苦しいというのも皮肉なものである。現代は緩和されてきているけれど、いつの時代もお金や人脈、コネ、学歴なんかはいわゆる成功者の条件だろう。そして、今作の描かれている時代には、それらに加えて非ユダヤというのも成功する条件の1つ。そんなバックグラウンドも描かれている点が他の物語ではあまり見られなく、物語を深刻化する要因にもなっている。
父は熱心なユダヤでありながら、サリンジャーはそこへ馴染むこともできず自分の進むべき道についても悩み、それで最終的には小説家になるという夢を追う物語になっている。今作はいわば自伝的なサクセスストーリーに仕上がっているのだけれど、宗教や家庭環境、恋愛、戦争など様々な要素が絡み合っており、単なる1人の人間のサクセスストーリーと捉えるには事足りないほど、複雑な要素が散りばめられ複雑な設計によって物語が構築されている。それだけ宗教絡みの葛藤というのは、当人にとって深刻な問題だということを示唆させるし、宗教以外の部分にも破門していくようだ。僕自身、自分が信仰するという意味では宗教に全く関心がないので、自分ごととしては本質的な理解はできないが、物語として、そのストーリー性やドラマチックな作風は映画として一見の価値はあるだろう。それに加えて、アーティスティックな演出や映像が補完的に物語を引き締める。
孤独の中で言葉があふれ出す
これが今作のキャッチコピーのようで、僕にとってこの上ないほどキャッチーなワードだった。そして、このワードが添えられている側に映るのが、煙草を手にするニコラス・ホルト演じるJ・D・サリンジャーになるわけだが、もうこのジャケットが異様に格好良い。実際、僕が今作を見ようと思ったのはこのジャケットといっても過言ではない。というか、その通りだ。
また、ニコラス・ホルトのビジュアル的な面はもちろん演技力についても、僕は絶妙なキャスティングだと思った。というのも、「ユージュアル・サスペクツ」や「アメリカン・ビューティー」で衝撃的な役者だと感じたケヴィン・スペイシーが出演してるから。彼の演技にも注目しておきたいところ。映画を構成する要素は無数にあるわけだけれど、今作はこの2人の役者でほとんどが成り立っていると感じた。それくらい2人の演技から物語の、そして当人達の機微を感じるには最適なキャスティングだった。
そして、「孤独の中で言葉があふれ出す」というのは紛れもなくサリンジャーのことであって、先程のユダヤ関係もあり孤独という葛藤を放出するために物書きをしている訳だ。社会への溢れる憤りや葛藤を物語にするのだから、それは面白いはずだ。僕も原作をぜひ読んでみたいと思っている。少し古い考え方をするならば、何かを成すには過去に強烈な”ディス”があることが多いように感じている。それがエネルギーになり、途轍もない成果を叩き出す。逆境に身を置いた人の方が強い傾向にあるのはそのためだ。温室でぬくぬくと育った人よりも確かに前者の方が有用性を感じる。僕は正直過去へのディスはありながらも、ぬくぬくしているようにも思うので、結局どっちつかずだ。これが良いのか悪いのかはわからない。そういうぬくぬくの社会になったのも先人の努力の賜物だと思いつつ、もっと貪欲になる環境・社会にしなければ経済はよくならないのでは、と思ったりする。
最後はまたまた逸れてしまったけれど、美しいコピーにジャケットから引き込まれて、反ユダヤや物書きとして抱える憤りや葛藤など心理的描写などドラマチックな物語に、ニコラス・ホルトとケヴィンスペイシーはベストマッチ。一度見ても損はないだろうという作品。