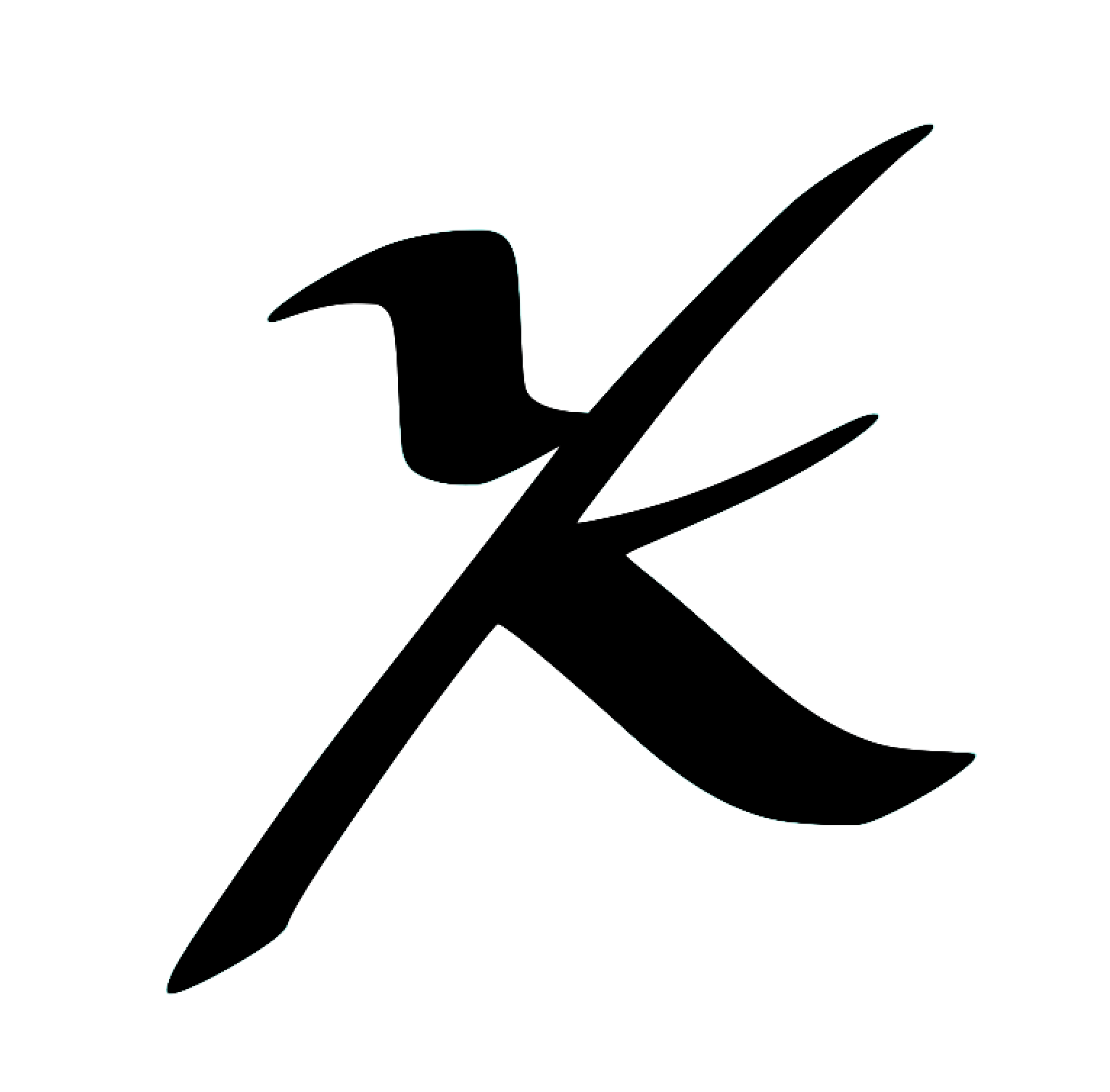癖のあるタイトルだからこそ大きなカタルシスが生まれる。
社会問題は母親にあると言う問いに、性別の本質的な側面から迫るアカデミックな作風。
そして、コミカルだけれど、確かな教訓のある素晴らしい映画。
作品情報
制作年 2001年
制作国 アメリカ
上映時間 97分
ジャンル ドラマ、ロマンス
監督
トニー・ゴールドウィン
キャスト
アシュレイ・ジャッド(ジェーン)
グレッグ・キニア(レイ)
ヒュー・ジャックマン(エディ)
マリサ・トメイ(リズ)
エレン・バーキン(ダイアン)
あらすじ
人気のトーク番組で働くジェーンは、新任のプロデューサー・レイと恋仲だったが、同棲を始めようとした頃、レイは急に別れ話を持ち出した。
彼への苛立ちを同僚の構成作家兼プロデューサー・エディの家に転がり込むことで解消するジェーン。
彼は傷心のジェーンには温かく接してくれたが、ジェーンはある新聞記事に衝撃を受け、狂ったように動物の研究に打ち込む。
やがて彼女の研究に親友の編集者リズが注目、有名男性誌にコラムを連載、大反響を呼ぶ。
そんな折に、別れた恋人と偶然再会して落ち込むエディの姿を見たジェーンは、自分の理論に疑問を抱きはじめたが…。
感想・考察
これぞキャスティング 的な俳優陣
まず、今作の特筆すべきは俳優陣の顔ぶれが凄まじいこと。
アシュレイ・ジャッド、グレッグ・キニア、ヒュー・ジャックマン、マリサ・トメイ、エレン・バーキン。
そうそうたるメンバーだ。
そして、監督もトニー・ゴールドウィン。
彼は、「ゴースト/ニューヨークの幻」の悪態っぷりが高じて一気に有名になったよう。
彼の表情からは冷酷な印象を受けるけれど、イケメンっぷり故に、その具合が何処か心地よくもあったりする。
まあ、言ってしまえばイケメンなら大体のことはポジティブになるという。
癖のあるタイトルだから生まれるカタルシス
冒頭のモノローグを語るのは、
「感情には、理性で測れない理由がある」のパスカルとジェーング・ドールの「新しい雌牛理論」
これが、結果的に物語に対して網羅的に関わってくる。
引きの効果は抜群で、僕自身もなんだか頷いてしまった。
これはいわゆる”ストーリーテリング”になる訳だけれど、それが妙にうまく、冒頭からトニー・ゴールドウィンのマルチぶりに感銘を受けてしまう。
安直だけれど、タイトルから想起したものとは別物だった。
僕なら、このタイトルであれば男女のドタバタ恋愛コメディチックな作風を思い描く。
それが冒頭のアカデミックな問いかけで、さらりと塗り替えられた。
それによって、この映画に対する好奇心でいっぱいになった。
なんにしても、ギャップは好奇心を誘発させる。
今作であれば、タイトルとモノローグのギャップが良い意味で不一致したことだった。
大体の人であれば、タイトルに惹かれて映画もDVDでも番組でも手に取る訳で、その時に大なり小なり好奇心(ワクワク感)を覚えている。
だから、もっと知りたくて、手にとって、そして見るという行為に至る。
最初にタイトルから得た好奇心と内容が悪い方でギャップがあれば、映画評がそれを貶す。
タイトルの一人歩きのような感じ。
見る前の僕は、安直そうなタイトリングのせいか、監督が俳優出身のせいか、今作はタイトルの引きの割に内容が薄いなと感じでしまいそうだった。
けれども、それが良い意味で覆された。
キャッチーな癖の強いタイトルに、アカデミックなモノローグに、個がたつけれど映画中では良い意味で丸くなった俳優陣によってカタルシスが生まれた。
端的にいってしまうと、タイトルのせいでネガティブに予想していた映画が、予想を超えて良かったということ。
それも、内容だけで構成されたものではなくて、タイトリングから内容、俳優陣、監督といった網羅的な要素が合致して噛み合っているのだから、今作は凄い。
これだけ色々書いて、結論が凄いというのもまた安直だけれど、とにかく凄い作品だと感じたのが率直な感想。
「社会問題は働く母親に責任がある」という
作中には他にも引きの効果がたくさんあったけれど、印象に残っているのは、
”社会の問題は働く母親に責任がある”という主張。
そして、それは”家庭の危機”だという。
結果的に、”女性の働くことは野心的で家庭での役目をおろそかにしている”とまで言う。
随分と過激で挑発的、よく言えば挑戦的なワードを並べている。
結局、このシーンは、ジェーンの働く会社の企画で”知的で挑発的なトークショー”を作るための算段なのだけれど、序盤で挿入することで、またもや引きを作ってくる。
そして、その後の注射のシーンでは、注射をするにあたって男性は躊躇するが女性は迷いなく一発で済ます。
これもまた面白い。
端的にコミカルでもあるのだけれど、女性が決断力や実行力に優れていると言うことを伝えていると思う。
結果、女性の働くことを是正する効果がある。
と言うのも、働き方によって色々あるけれど、企業の経営側に携わる人は毎日が決断と実行だからだ。
経営側には男性が多いと言う現状があるけれど、本質的にその立場に向いているのは女性であると言うことを伝えている。
どこまで意図して作られているのかわからないけれど、僕にはこれらのシーンがそう映った。
コミカルで楽しめる演出が豊富だけれど、終着点も明確
ここまで、アカデミックやら何やらと語ってきておいて何だけれども、今作の娯楽性は高い。
ブラックジョークを交えた言葉選びや演出の音楽も絶妙で端的に余計なことを考えずに楽しめる作品でもある。
つまり、コミカルな側面とアカデミックな側面。
どちらから見ても楽しい映画で、これがまた凄い。
だから、ジャンル分けをするのも難しい。
アカデミックでロジカルなシーンもあるし、コミカルなシーンも満載。
ベースにあるのは人間模様を描いたドラマでもあるし、男女間のロマンスもある。
ドキュメンタリーチックな牛の実験のシーンもある。これらが喧嘩せずにいるのが今作で、その作風たるや素晴らしいに尽きる。
結果的に、クライマックスでは、意外な人物(個人的に)とジェーンが結ばれる。
そして、そこで伝えているのは”自分の本質に向き合う”と言うこと。
何かに悩むのも葛藤するのも、結局のところ問題は自分の中にあって、変えることができるのも自分次第。
そんな教訓的なこと、また良い。
そして、ジェーンと彼が抱き合う後ろには、牛の姿と言うのもまた面白い。