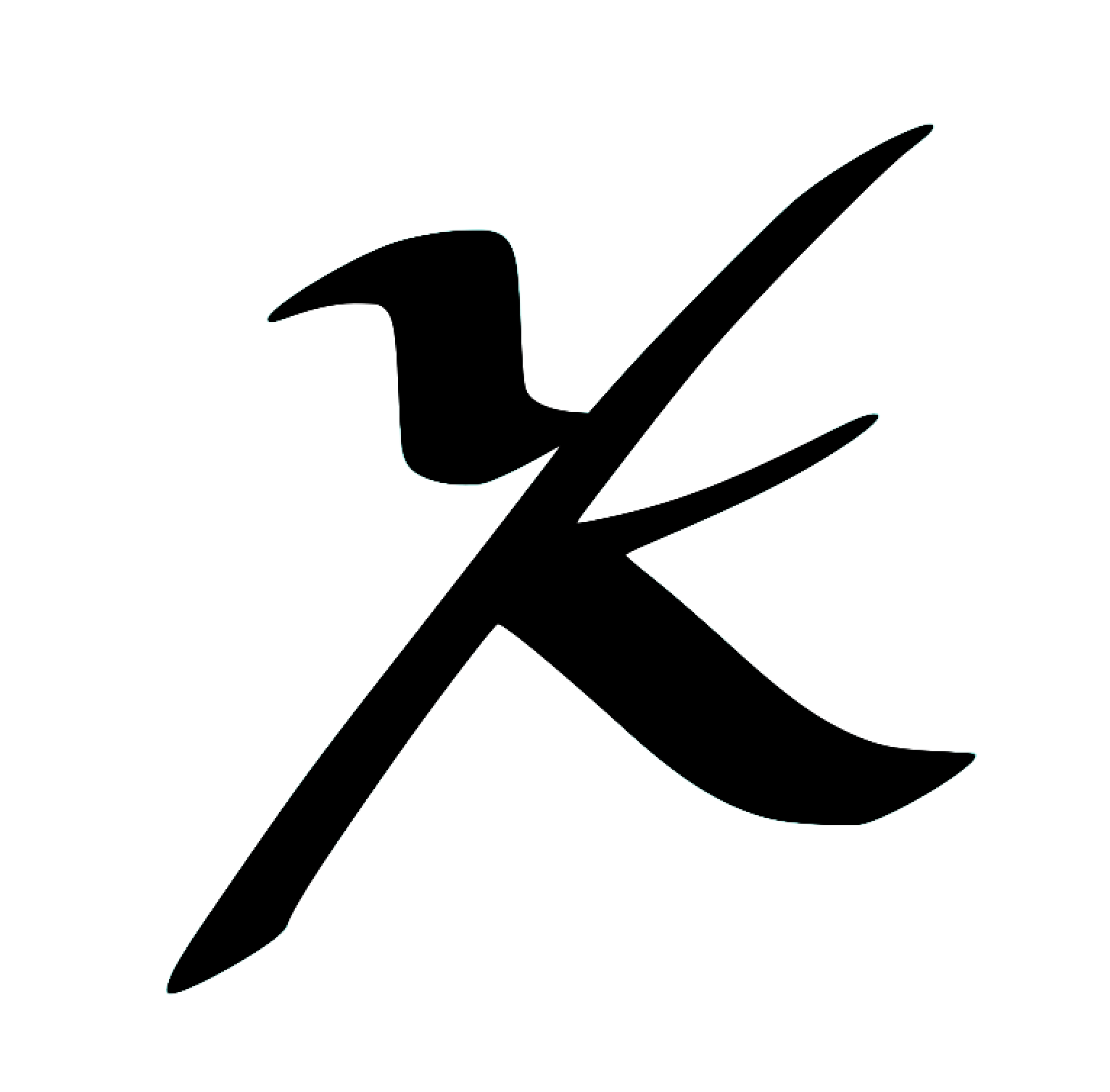映画の見方に正誤はありません。
今作は映画的メディアでありながら、映画的芸術作品といえるでしょう。
今作は「映画はどう味わい、何を感じるか。それは自分次第です。」と、考えを訴えられているようでした。
言い換えれば、ヌーヴェルヴァーグという映画のムーブメントはもとより、創造物における表現の自由を強く訴求しているように感じます。
作品情報
製作年 1965年
製作国 フランス
上映時間 105分
ジャンル ドラマ
監督
ジャン=リュック・ゴダール
キャスト
ジャンポール・ベルモンド(フィルディナン=ピエロ)
アンナ・カリーナ(マリアンヌ)
グラッツィラ・カルバーニ
ダーク・サンダース
あらすじ
妻子持ちのフェルディナンは、妻の付き添いパーティに参加したものの、倦怠を覚え帰宅することに。
その途中、幼馴染のマリアンヌに出会い彼女と一夜を共にし、彼女宅で目を覚ました彼は、部屋には血まみれの、あるものが転がっているのを見つける。
それから彼らの逃避行が始まる。
感想・考察
ヌーヴェルヴァーグとは
ある程度、網羅的にあれやこれやと映画を見てきたものですが、ヌーヴェルヴァーグなるものに出逢いまして、トリュフォー、ゴダール作品というのを見てみようと今回の作品に至りました。
ヌーヴェルヴァーグとは、1950年代にフランスで起った映画におけるニューウェーブの事で、下積み経験の未熟な、または下積みなしの若手映画監督による自由な作風の作品群の事を指します。
映画に例えれば、ヌーヴェルヴァーグ作品を語ってこそ映画通であるような風潮も見られます。
そのような玄人目線の映画評や自意識の反発こそがヌーヴェルヴァーグのようなムーブメントの原動力かも知れません。
言い換えれば、既存のスキームに縛られ新規性のあることを蔑むような社会規範とも取れるような姿勢の反骨心がヌーヴェルヴァーグのエネルギーであります。
現代社会に置き換えれば、年功序列制のような社会システムに反発し、自分でビジネスを起こしたり、中年サラリーマンよりも稼ぐような若者も一種のニューウェーブであり、今後の希望でもあります。
単にヌーヴェルヴァーグ作品を見ようとも、その新規性は腑に落ちるものの、それがなぜそこまで肥大化したのかはを論理的に語ることは困難でしょう。
しかし、現代に置き換えたときに、現代の若手起業家が注目を集めるように、ビジネスであれ映画であれ、新規性のある創造物を構築する事のそれは、大きなポテンシャルを秘めており、言葉では言い表せない奇妙さ覚えるような、好奇心を刺激するのではないでしょうか。
そんな言葉では言い表すことの難しい良さがこの作品にはあります。
映画を視覚的に楽しむというよりは、当時のニューウェーブ、ムーブメントといった歴史を知ることでより一層楽しめる作品です。
自己表現としてのアートと創作物としてのアーティファクト
芸術を自己表現とすれば、この作品から、その要素は遺憾無く感じます。
しかし、あくまで作られたアートであり、アーティファクトという言葉が似合うのです。
いわば、単純な自己表現とは違います。
だからあくまで映画的に作られたアーティファクトであると感じるのです。
今作が意図的なアーティファクト的な映画であるとすれば、そのまま具現化されら芸術的な作品として「尾崎豊」を思い浮かべます。
彼の歌を聞けば、彼自身の体感である葛藤や愛、痛みが心の叫びとして吐き出され歌という形で表現されたアートを感じるのです。
彼の歌にはそんな悲痛な自己表現がアートを感じるのです。
タイミングによりけりですが、彼は歌うのが苦しそうで。
彼の資本主義に対する揶揄的な思考による歌詞や表現からも心からの自己表現ということが汲み取れます。
尾崎豊的な自己表現としてのアートにしろ、気狂いピエロ的な創作物としてのアーティファクトにしろ、非常に主観的なので議論には至りません。
しかしながら、今作にはゴダールのクリエイターとしての葛藤や悲痛さも感じるのです。
あくまで映画に縁取られた映画的なアートですが。
人生をどう生きるかという万人の共通項
フェルディナンの「ただ生きる、それが人生さ」という台詞の趣旨にこそ、どう感じるかは自分次第。というメッセージを感じます。
万人に与えられている1つのテーマである人生に対して”ただ生きる”というのは少々乱暴でもありますが、大衆的に当然の共通項でも腑に落ちるところでもあります。
その人生を生きるというテーマに沿って、どう生きて、人生に経験を上書きしていくかは自分次第であります。
インターネット的なフラットな社会になって久しいと現代ですが、これをこの映画的に考えれば自己表現の容易さにゴダールは驚愕するかもしれません。
彼は去年も新作を発表していますが、なんて表現しやすい社会になったのだろうか。と感じているかもしれません。
それを補完する形で映画評には、彼の作品のクオリティーは落ちたと言われていました。
言い換えればやはり彼の作品や創作物というのは柵があるからこそ、所謂良いものであり、人を感化させるパワーを持つのかもしれません。
当時の社会といえば現在の社会にも、増してトップダウン的な社会だったのでしょう。
家庭も仕事も。だからこそ、その憤りが作品を超えて、ムーブメントとして後世にも語り継がれるヌーヴェルヴァーグが構築されたのでしょう。
だから現代の彼の作品は以前よりも容易に制作できるが故にクオリティーが落ちたわけです。
斬新な表現とメッセージ
台詞は音楽によってかき消され、音楽だけが流れるシーンがいくつかありました。
当然、何を言っていたのかは分かりません。
それについてもゴダールは映画監督として映画という形で、何かを考えるきっかけは作れるけど、映画の捉え方にも答えはないとメッセージをくれるのです。
そんな音声以外にも、彼のメッセージを感じるシーンがありあます。
物語であるはずが、敢えて、なぜその事柄が起こってしまったのか。
を描かないという点です。一般的に見せる事が芸術であるけれど敢えて見せない、聞かせないということに何処と無く芸術性を感じたりなどするのです。
マリアンヌの「あなたは言葉で語りかけ、私は心で答える」という台詞が印象的です。
愛を口先だけで語る男を揶揄しているようです。
自分も思い当たる節があるというのは口を慎んでおこうと思います。
社会を映す映像的メディアか語るか、そのバックグラウンドを語らうか
今回も全く意図的ではなくてベトナム戦争について触れられているシーンがありました。
それらの映画にあったのは戦争を社会的なメディアとしてネガティブを後世に伝える役割です。
しかし、今作においてのベトナム戦争は、それではなく。
フェルディナンとマリアンヌにとっての身近になってしまった犯罪との対比として描かれます。
対比といってもフランスの彼らにとっては挙げた作品ほどの主体性はないので、単なる比喩でもあります。
難解な作品、けれどそれが醍醐味
正直、難解な作品でした。
映画通には、この手の作品は面白いと言われるのも確かに腑に落ちます。
しかし、それは映画通の映画や歴史に関する事前知識があって映画を見るからです。
自分にとっての今作単品では、そもそも何を伝えたいのかわかりませんでした。
しかし、それというのがゴダールの1つの解であると思うのです。
だから冒頭で書いた「映画はどう味わい、何を感じるか。それは自分次第です。」と言われたように感じるのです。
だから、こそ歴史的背景を考えれば見えてくるものがありました。